🔰 第1段階|家計管理:保険の本質を知ろう
教習指導員パパが運営する【お金の教習所】へようこそ!
「掛け捨て保険って、なんだか損した気分になる…」
「どうせ戻ってこないなら、入らない方がいいのでは?」
そんな声をよく聞きます。
でも実は、**掛け捨てこそが“保険本来の姿”**なんです。
今回は、保険の本質や必要性について、損得ではなく“本質的な視点”から一緒に見直していきましょう。
✅ この記事でわかること
- 掛け捨て保険は本当に損なのか?
- 保険の本来の役割(=相互扶助)とは
- 自分にとって保険が「いる・いらない」の判断基準
🔍 そもそも「保険」ってなんのためにある?
保険の本質は【相互扶助(そうごふじょ)】。
これは、お互いに支え合う仕組みです。
たとえば…
あなたが突然亡くなってしまったとき、残された家族が困らないように――
保険は「もしもの時」に備える“助け合い”の仕組みなのです。
つまり、自分が得をするための商品ではなく、“人を守るため”の備え。
🧾 掛け捨て保険は「損」じゃない。むしろ自然な形
掛け捨て保険とは、保険料が戻らない代わりに、安い保険料で大きな保障が受けられる保険。
✔ 掛け捨て保険のメリット
- 月額が安く、必要な保障が得られる
- 保障期間が明確で、目的に合っている
- シンプルで見直ししやすい
よく「元が取れないなら損」と言われますが、
保険は「起きてほしくないこと」に備えるものであり、
**“使わない=良いこと”**でもあります。
🧠 本当に保険が必要なのはどんな人?
結論から言うと、「自分が亡くなったときに困る人がいるかどうか」が最大の判断基準です。
🟢 保険が“いる”ケース
- 子どもが小さい(教育費や生活費が必要)
- 自分が収入の柱で、パートナーの収入が少ない
- 住宅ローンなどの返済が残っている
- 高齢の両親を扶養している
🔴 保険が“いらない”ケース
- 独身で扶養すべき人がいない
- 共働きで、片方が亡くなっても生活が維持できる
- 子どもがすでに自立している
- 生活防衛資金や資産が十分にある
👉 **つまり「亡くなったときに困る人がいないなら、保険は不要」**という判断もごく自然なことなんです。
💡 じゃあ、どんな保険に入るべき?
私がオススメするのは、シンプルに以下の2つ:
1. 掛け捨ての定期生命保険(期間限定で保障)
👉 子育て世帯など、一時的に高額保障が必要なときに
📊 図解:掛け捨て vs 貯蓄型の違い
| 特徴 | 掛け捨て型保険 | 貯蓄型保険(終身など) |
|---|---|---|
| 保険料 | 安い | 高い |
| 戻ってくるお金 | なし(掛け捨て) | 解約返戻金あり |
| 保険期間 | 一定期間(例:60歳まで) | 一生涯 |
| 柔軟性 | 高い(見直ししやすい) | 低い(途中解約は損) |
| おすすめ層 | 守るべき家族がいる/貯蓄優先したい人 | 貯金が苦手/“終身”に安心感を求める人 |
2. 収入保障保険(亡くなったら月々の生活費が支給される)
👉 働けなくなった場合の生活維持に役立つ
💬 貯金が少ないうちは保険で備え、
十分に貯められたら徐々に保険を手放すのが王道です。
📌 まとめ:保険は「損得」で考えない
- 掛け捨て保険は損ではなく、「本来の保険のかたち」
- 保険は、“自分がいなくなった時、誰が困るか”で考える
- 保険と貯蓄、どちらも「目的に合わせて」使い分けよう

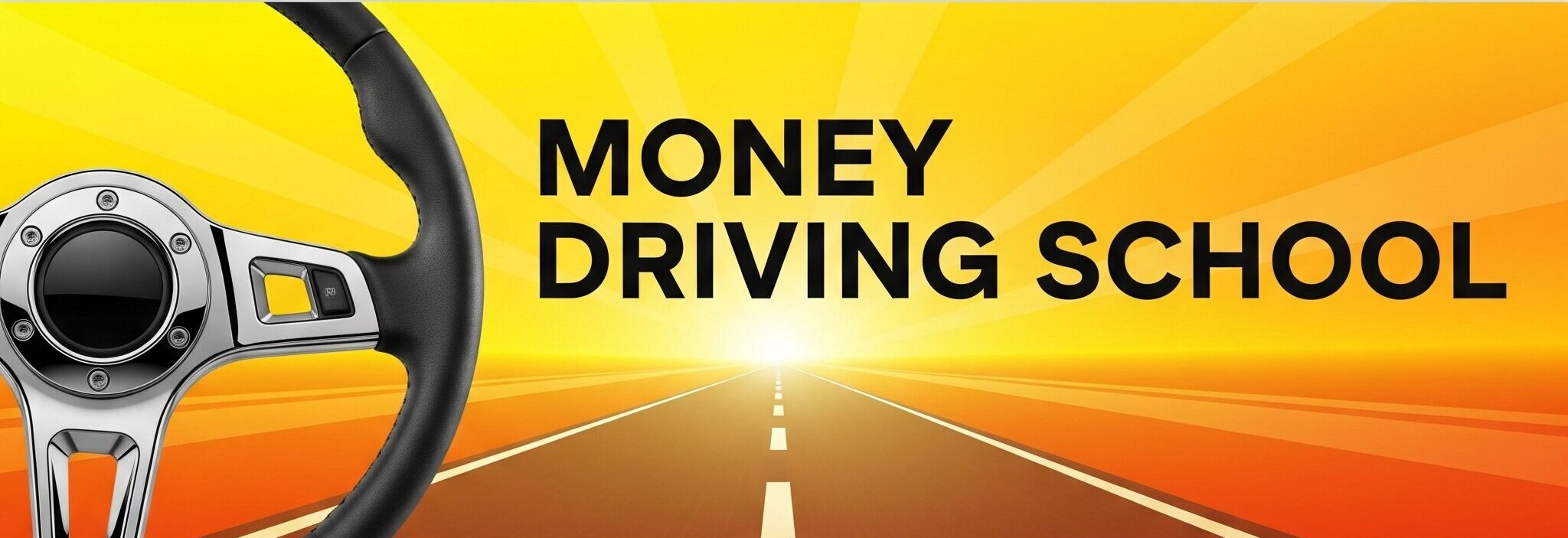


コメント